◆◇ Special Study: ラテン語系言語から観たcould (私見です。)◆◇
ラテン語系の言語では、直説法・接続法という、話者の立場で、動詞の活用が
2つに分かれています。また、ドイツ語にも接続法がありますね。
私が学んできたラテン語系言語では、
□直説法は、事柄を●客観的な事実●として表現する方法
□接続法は、(多くは従属節の中で)●主観的な心理の状態●を表現する方法
です。
日常会話に多く出てくる表現は、間違いなく接続法の活用の動詞です。
つまり、少しでも、感情の入った表現、または、私はこう思うのですが・・・、
という、話者の主観的な意見等を表現しようとする時には、必然的に活用は接
続法になるからです。
ですから、主節に、I wish とか、I’m sorry などが来た場合は、ラテン語系
言語では、それに続く従属節には、接続法、の動詞の活用が適用されます。
ところが、英語には、直説法・接続法に対する、動詞活用の変化がありません。
その代わりとして、英語では、動詞を活用させるのではなく、助動詞に変化を
つけて補っている、ということが言えるかもしれません。
そこで、can を接続法的に活用したものが、会話などで頻繁に使われている、
このcould である、といえばどうでしょうか。
I’m sorry が主節で、その後が従属節。ラテン語系言語ならば、次に来るのは、
“主観的な心理の状態”の表現ですから、接続法の活用形となります。
ですからその従属節の中では、can’t というような直接法の言葉はふさわしく
なく、couldn’t というような、接続法的な言葉がマッチしてきますよね。
∴『can の”過去形”が could 』という文法知識以外にも、
『can の”主観的(接続法的)形”がcould』 ということを意識すれば、
すっきりと理解できそうです。多くの場合、過去ではありませんからね。
Could be. かもね、(事実かどうかしらないけど)。
=(I think it) Could be (true).
というのも、主観的な意見を述べているので、can be (~だという可能性も
ある)という客観的な事実をそのまま伝える形から、could be という接続法
的な表現になっていると思えば、たやすく理解できます。
I’m sorry she couldn’t be here today.
I wish I could fly.
(I think) He could be related to our present threat.
・
・
・
ラテン語系の言語では、日常会話では、接続法の方がむしろ多く使われていま
す。会話をするのに、接続法の動詞活用をたくさん覚えなければなりません。
そういう意味で、英語でも、could が頻繁に会話の中にでてくるのは、むしろ
自然なことかもしれません。で、could が普通に使えるようになれば、かなり
ネイティブらしい表現ができるようになる、というところです。
ドラマ・24の英語をピックアップしながら見ていますが、会話で、could が
使われている場面が多くでてきます。could はなかなか難しいですね。これか
らも、いろいろと試行錯誤しながら、理解して行こうと思っております。






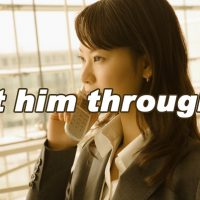

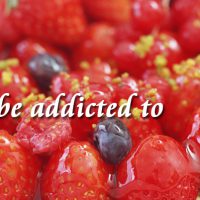






この記事へのコメントはありません。